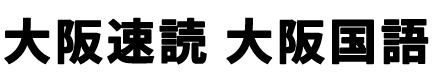【中学受験】女子最難関「桜蔭離れ」が起きている?
【中学受験】女子最難関「桜蔭離れ」が起きている?
東京・大阪の中学受験国語専門塾
パワー読解新宿・大阪国語
https://osaka-sokudoku.jp/jukenkokugo/
今津です。
新宿で書いています。
首都圏では女子最難関校として知らない方はいない桜蔭中・高等学校でここ数年異変が起きているのをご存じでしょうか。
桜蔭といえば、女子校の中で東京大学への合格者を多数輩出する学校であり、女子御三家のうちの一つとして大変有名な学校です。
女子御三家はこの桜蔭の他に、女子学院と双葉があります。いずれも最難関校として知られています。
桜蔭は1930年創立で、東京女子高等師範学校(現在のお茶の水女子大学)の同窓会である「桜蔭会」が母体となり設立された学校です。
清楚で礼儀正しいイメージのある学校です。実際に中学の間では週1時間の礼法の授業があります。
高校入試は存在していません。
東京大学の合格者は女子校首位を保っています。
2014年度は66名、15年度は76名と10名増になっています。
このときの卒業生は232名ですから、その中に占める東大合格者は約33%です。
なんと、3人に1人が東大生になっているわけです。すごすぎませんでしょうか?
他に東京科学大(東京工業大と東京医科歯科大が2024年に統合して設立)への進学者も多数います。
この桜蔭において、それ以降徐々に人数が減っていき、2025年度入試の東大合格者は52名となってしまいました。
学習塾業界の界隈では「桜蔭離れ」と言われています。いったいあの桜蔭がどうしてしまったのでしょうか。
【大学入試は専門ではないのですが…】
大学受験指導を個人塾時代に行っていたにはいたのですが、もう離れてしまって久しいですし、そもそも大阪で関関同立や地方大学を指導していたので首都圏の大学受験の指導経験がありません。
なので、ここからはあちこちの情報をツギハギしながらお伝えします。
52名とはいえ、それでも2025年度入試において女子校の中では東大合格者数は1位をキープし続けています。
ちなみに2位以下を並べてみます。
2位は洗足学園28名、3位は豊島岡19名、4位双葉15名でした。
2024年度において、1位桜蔭63名、2位豊島岡26名、同じく2位女子学院26名、4位洗足学園15名でした。
24年から25年にかけては洗足学園がすごく伸ばした印象があります。15名から28名です。
なぜあの桜蔭がこういった状況になったのでしょうか。
一つには、共学志向が強まっていることかもしれません。
中学受験の現場にいて昔と違う点が、共学志向の高まりです。
女子校の人気に陰りが出ていることは否定できません。
もちろん全部の女子校の人気が下がっているわけではないのですが、どちらかといえば共学に行きたいと考える女子のお子さまが多くなっていることは肌感覚ですごく感じます。
関西においても同様で、帝塚山学院などの超人気校は別格として、女子校で以前と比べて元気のない学校はいくつも存在します。
共学校である渋谷教育学園渋谷では、東大合格者が2022年においては38名、23年は40名、24年が43名、25年が50名と右肩上がりです。
渋渋の教育活動が結果に結びついていることはもちろんだと思いますが、それ以外の要素として、優秀な女子のお子さまが共学である渋渋に流れていることがあるかもしれません。
しかし、それが理由のすべてだとすると、何かひっかかることがあります。
女子校の洗足学園がどうして東大合格者を伸ばしているのか、ということです。
洗足学園では塾に頼らずに合格実績を作ろうと真剣に取り組んでいて、メタ認知力の向上に力を入れていることも結果に結びついていることが考えられます。
以前にブログや動画で取り上げたのですが、メタ認知とは、自分が考えたことなどを第三者の目線で客観的に見ることを言います。
ついつい自分主体でものごとを考えがちですが、自分が考えたり表現したことを、自分以外のいろんな視点から多角的に考察することって、意外にできなかったりします。
メタ認知力は最近大学入試で注目されていて、多角的に考察できるかどうかを問う出題が顔を出しています。
昔ならばとんでもなく難しい問題を解けるかどうかが大切だったり、他人よりも圧倒的にいろんなことを知っていることが合格のカギだったりしました。
今はそれらの影がすっかり薄くなり、難問奇問のたぐいが随分減っています。
難問奇問よりも、教科書を丹念に理解できているか。
ここにポイントを置く出題が増えており、その結果難易度が下がってきつつあります。
また、入試形態そのものも多様化していることとも関係があるかもしれません。
一般入試に限らず、総合型選抜もメジャーとなりました。東大ですら総合型選抜方式による入学者は2割もいます。
ということで、東大の二次試験の難易度が下がったのが原因だという説が濃厚ではあります。
しかし、それだと桜蔭が一人負けしている説明がつきません。
あと考えられることといえば、桜蔭という学校そのものを選ばない女子のお子さまが増えたという説です。
また、桜蔭のような超難関校でなくとも、それ以外の学校において二次試験の難易度が下がった東大を目指すことができてきたということも一因にあるようです。
【この現象から言えることは何か】
桜蔭の人気に陰りが出てきたとか、魅力が薄くなったということではないとワタクシは考えています。
そうではなく、いろんな流れを読み取って東大が多様性を求めた結果、入試も多様性が出て、入学者にも多様性が出た。
以前とは違い、入学者の出身校にも多様性が出てきつつあるというのが本当のところではないでしょうか。
中学入試をお考えの皆さまは、そのことを念頭に置きつつ学校選びをしていただければと思っています。
ついついどこの大学に何名通したかなどを気にしがちですが、それよりもどのような教育理念を持っているのか、またどのようにしてその理念を落とし込んだ教育を実践しているのかを丹念にチェックしてください。
それらとあなたのお子さまが合っているのかどうか。
ここが一番大切なポイントであり、わざわざ中学受験をしてまでして学校をお選びいただく最大の目的でもあります。
#中学受験 #東京 #大阪 #名古屋 #SAPIX #日能研 #早稲田アカデミー #四谷大塚 #浜学園 #国語
#千葉県 #神奈川県 #横浜 #埼玉県 #茨城県 #京都 #神戸 #豊中 #世田谷 #中野区 #品川 #目黒 #港区 #杉並区 #豊島区 #西宮 #芦屋 #茨木市 #高槻市 #吹田市